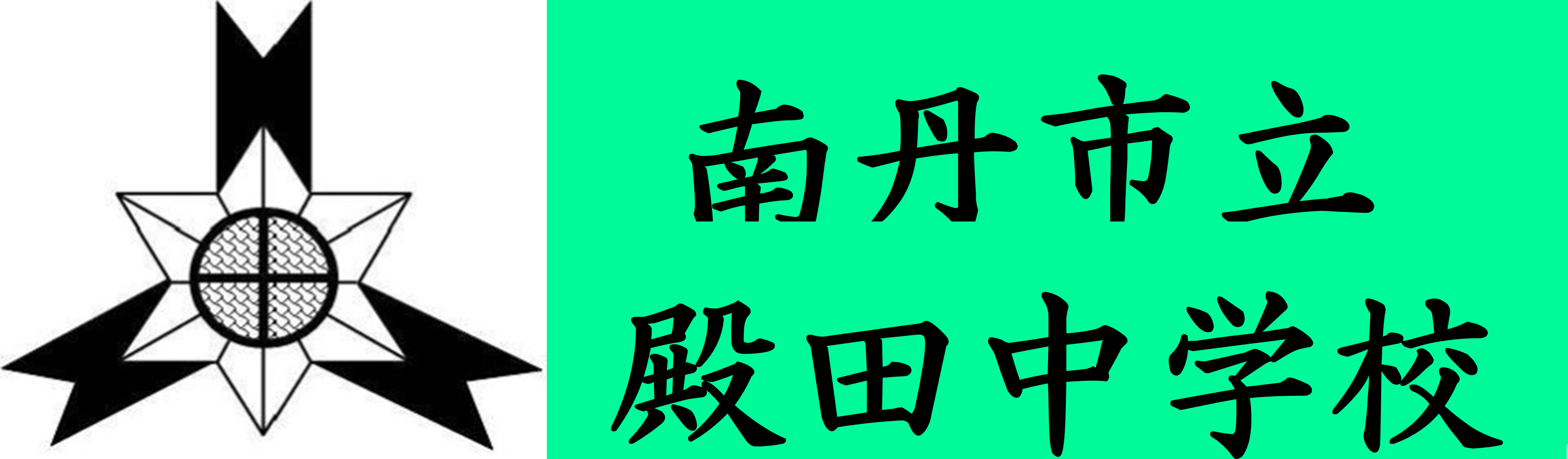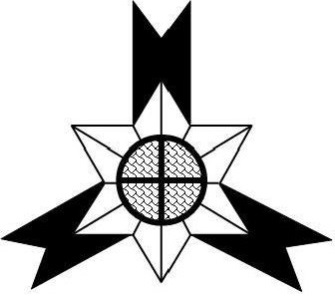公共心を養う
朝夕の冷え込みが増し、秋の深まりを感じる季節となってきました。新型コロナウイルス感染が一定治まったものの、冬場に向けて第6波の襲来やインフルエンザの流行に備えて、引き続き感染防止対策を徹底しながら、油断することなくマスク着用、手洗いやうがいを励行して健康管理に努めてほしいと願っています。
さて、延期となっていた修学旅行・校外学習等を体調不良や事故等もなく無事に終えることができ、本当にほっとしています。また、皆さんは普段とは異なる場所で、様々な人と触れ合い、様々な経験をすることができました。校外での学習には様々な目的がありますが、そのうちの一つに「公共心」を養うことがあります。簡単に言えば「公共心」とは、公共の場(社会)での、人としての望ましい行動力や、他の人に迷惑をかけない、嫌な印象を与えないために守るべきマナー等のことです。乗り物(公共交通機関)の中ではどんな風に過ごすべきか(正しい座り方、大声で騒がない)、多くの人が行き交う駅舎ではどのように電車を待つべきか(広がって通路をふさがない)等、3年生は修学旅行で身をもって学習しましたが、それ以外に身近なところでも様々な公共マナーに反することがあります。例えば、先日も指導しましたが、自分たちの勝手な都合で電車乗車口から降車することが電車の出発遅れに繋がること、登校時に集団で歩道いっぱいに広がって歩くことが近隣住民の方の通勤の妨げになること、校門周辺での車に道を譲ろうとしないことが安全面はもとより来客や地域の方々に嫌な印象を与えることなどです。
世の中には「TPO」という言葉があります。「時(Time)」と「場所(Place)」と「状況(Occasion)」をわきまえた振る舞いが必要だという意味です。校内や登校途中にも小さな社会が存在し、私たちの行動一つ一つが様々な社会と繋がっており、私たちもその社会を意識した行動をすることが求められます。例えば図書室は静かに読書する場所である、来校された方にも気持ちの良い挨拶をする等です。公共でのマナー違反は、他人が行っている場合はよく目につきますが、自分が他人に迷惑をかけている、良くない印象を与えていることは案外気が付かないものです。私自身も皆さんと一緒に、自分が公共マナーに反する行動をとっていないか、自分の行動をかえりみることを心がけたいと思っています。
「規則」を守ることは当たり前です。もう一歩進んで、「善い行いと善くない行いを自分で判断して実行する態度」や、「規律」を守る心を養うために「正しい判断力と他人を尊重する心」を鍛えていくことが人としての土台であり、社会人へのスタートラインとなるのだと思います。
後になりましたが、保護者の皆様には平素より本校の教育活動に格別のご理解とご支援をいただいておりますことに改めてお礼申し上げます。先日お知らせの通り、11月20日に「親子道徳」を予定しております。休日でもあり何かとご都合があるかと存じますが、子ども達の道徳性を養うためにぜひとも授業に参加頂き、子ども達と一緒に考え、大人・親の立場での思いを少しでも伝えていただければと思います。初めてのことであり、手探りの取組となりますが、どうぞご協力の程、よろしくお願い致します。
校長 世木 佳文