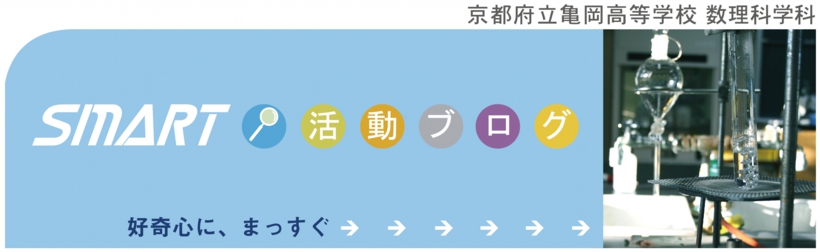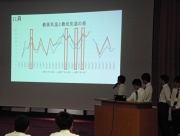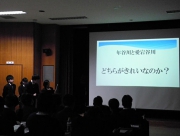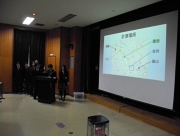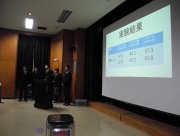グローバルサイエンス
第1回『京都サイエンスフェスタ』に出場!!
平成28年6月12日(日)に、サイエンス系統の専門学科を持つ京都府立高校生500名超が一堂に会して研究発表する「第1回京都サイエンスフェスタ」が京都大学で開催されました。本校数理科学科の1年生と2年生は聴衆として、3年生は10名が発表者としてフェスタに参加しました。高校生の発表とはいえ、それぞれに工夫がこらされており、レベルの高い内容でした。本校3年生は、「暗号の秘密!」(数学分野)と「亀岡の霧Ⅱ」(地学分野)の2班が発表しました。これを機会にサイエンスへの興味関心をより深く育んでくれることを願っています。2年生の岡哲也くんと内堀優香さんが、司会者として素晴らしい役割を果たしてくれました。2016.6.17



平成26年度 グローバルサイエンスⅠ 研究発表会(2015年2月23日)
2月23日(月)5・6校時に、今年度のグローバルサイエンスⅡ校内発表会を行いました。
4月から数理科学科一年生全員で亀岡市内を流れる河川の水質に関する研究を深め、グループごとに研究テーマを設定しました。今年度は特に、これまでの数理科学科1年生が行ってきた河川調査の結果や亀岡市HPのデータなどを活用し比較するなど、過去の調査結果を生かした研究成果が発表されました。亀岡市内の同一河川の経年変化、複数の河川の特徴の比較、同一河川の複数地点の状況比較、亀岡市内を流れる河川の全体像などに着目した様々な視点からの研究成果の発表が行われた後、活発な質疑が行われ大いに盛り上がりました。また、京都学園大学 バイオ環境学部 准教授 辻村 茂男 様の御講評の中、研究テーマや仮説の設定の際に必要な視点などをお示しいただき、その後まとめた研究レポートの充実に向けて大変参考になりました。各グループの研究概要は次のとおりです。
亀岡の河川調査:亀岡総論 (5名)
亀岡の河川調査:同一河川比較(6名)
亀岡の河川調査:経年比較1 (5名) …最優秀賞
亀岡の河川調査:経年比較2 (6名) …優秀賞
亀岡の河川調査:経年比較3 (5名)
亀岡の河川調査:経年比較4 (6名)
亀岡の河川調査:河川間比較 (5名)
<生徒の感想より>
・発表会に向けて、原稿をみんなで読みあったりと協力できた。また、人前でスピーチすることは難しいことがわかり、その練習ができてよかった。
・GSを通して身近な事柄を調査することも面白さやむずかしさについて学ぶことができ、もっと深く学んでみたいという意欲もわいてきました。
・研究成果を発表するプレゼンは、まとめの内容からあまり満足のいく結果にはならなかったが、来年のプレゼンでより良い発表が行えるようにしていきたい。
平成26年度 グローバルサイエンスⅠ
京都大学特別講義(2)「ヤツメウナギの生態について」(2014年9月30日)
ヤツメウナギの特徴
ヤツメウナギの生体を観察
化石からわかる生物種の特徴
9月9日に引き続き、京都大学大学院アジアアフリカ研究研究科より岩田明久教授をお招きし、ヤツメウナギについて講義していただきました。前回の講義でもヤツメウナギが大変貴重な在来種であることを学びましたが、今回はそのヤツメウナギの形態の特徴や生息域、生態についても詳しく学びました。講義を通して、絶滅危惧種を保護していくためには、特定の生物に注目するのみではなく、周囲の環境全体のバランスを考えながら保護を進めていくことが重要であることを学びました。
平成26年度 グローバルサイエンスⅠ
京都大学特別講義(1)「亀岡の外来魚について」(2014年9月9日)
亀岡市の外来魚の生態について説明
南郷池での釣り
実験室でのギル観察
京都大学大学院アジアアフリカ研究研究科 岩田明久教授の御指導により、亀岡市の外来魚について学習した後、学校近くの南郷池でブルーギルを釣り、その生態を調べました。
例年40~50匹釣れるのですが、昨年の洪水で水生ネズミであるヌートリアが激減したためか、水草が生い茂りギルは7匹しか釣れませんでした。が、そのギルは、水草が増えたおかげで繁殖したエビを食べて例年より大きく観察しやすかったです。食物連鎖の変化も実感できた実習となりました。
平成26年度 グローバルサイエンスⅡ 研究発表会(2015年2月20日)
2月20日(金)5・6校時に、今年度のグローバルサイエンスⅡ校内発表会を行いました。生徒一人一人が、研究テーマを選択し、約半年間取り組んだ研究成果を発表しました。発表グループのプレゼンテーションに対し、参加した他のグループの生徒や1年生を含めた活発な議論がくりひろげられるなど、充実した研究発表となりました。また、今回の発表に対して、京都学園大学バイオ環境学部 准教授 大西 信弘 様、同 清水 伸康 様に、全ての発表が終了した後、講評をいただき新たな視点も広げることができました。この研究について、各自でレポートを作成し、冊子にまとめました。各グループの研究概要は次のとおりです。
数学分野(6名):データの分析と検定
物理分野(6名):身の周りの音について
化学分野(5名):分子の大きさを測ろう … 優秀賞
生物分野(6名):亀岡の河川調査
地学分野(7名):亀岡の霧 … 最優秀賞
<生徒の感想より>
・約四ヶ月の研究を7分に収めることが難しく、発表は長くなってしまったが、言いたいことは言えてよかった。また、最初はデータを見てもなにもわからなかったものを、データ同士を合わせることでわかるようになっていけたのはうれしかった。来年もこの研究を続けて欲しい。
・1年生のときよりもプレゼンテーション能力が高くなっていたと思う。レポートも去年より時間をかけずに作ることができた。また質問に対することや相手に詳しくわかりやすく伝えることの難しさを知ることができた。GSはとてもよい経験だったと思う。
・自分は緊張して早口になり、さらに間違いがありせっかく大学の先生が来てくださっているのにこんな失敗をして、できることならやり直したいと思っています。また、質問に答えられなかったことも反省するべき点だと思いました。僕は理系の大学に進学するつもりなので、プレゼンテーションの機会もまだあると思います。後悔するだけでなく、次に行かせるように努力していきたいです。
平成26年度 グローバルサイエンスⅡ (2014年10月1日)
INTERNATIONAL DAY in KAMEOKA!
8名のゲストに来ていただきました。司会と挨拶は2年生です
ゲストは民族衣装を着て文化の紹介
クイズ形式の国の紹介も
1年生 クラスでクイズに挑戦①
1年生 クラスでクイズに挑戦②
9月26日(金)午後、数理科学科1年生と2年生が、京都市内の大学院で学んでいる留学生を8名お招きし、国際交流会を実施しました。
ブルガリア、カンボジア、ベトナム、インドネシア、マレーシア、中国の6か国の文化や高校生活などについて紹介していただいた後、2年生の代表生徒が亀岡高校や数理科学科について紹介しました。
その後、1年生はクラス全体でマレーシアとアメリカ(本校AETの出身国)と日本に関するゲームを通して交流を深めました。2年生は5人程度の小グループに分かれ、自分たちが作成した学校紹介パンフを利用しながら、様々な話題について交流しました。
この取組は全て英語で行いました。2年生にとっては、10月に実施するグアム研修旅行の事前学習の集大成ともいえるもので、この半年間英会話や英語でのプレゼンの練習をしてきた成果を発揮し、様々な英語をうまく聞き取り、楽しく交流することができました。
1年生は、留学生の話に即座に反応する2年生の姿を真近に見て、1年後の自分たちの姿に思いをはせました。