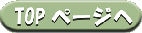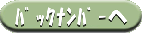| 「見る」には以下のアとイの2つがあります。 | |
|---|---|
| ア | イ |
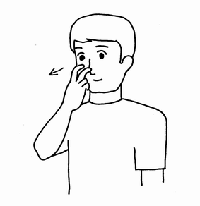 |
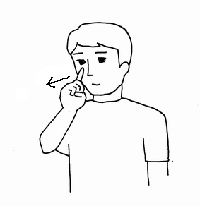 |
では、次文を手話で表してください。


次に、下の文をどう区別して表しますか?
| ① (私が)やってみる。 |
| ② (私が)やってみせる。 |
| ③ (あなたが)やってみせる。 |
特に①で、上記の「見る」(上の手話イラスト「ア」「イ」)
を使って表しませんでしたか?
「やってみる」と「やってみせる」を同じ表現にしないで、
① 「 ~してみる 」は、「試みる」
② 「 みせる 」は、「あらわす」
というように、区別して表現する方が、
手話を読みとって勉強する子どもにはより正確に伝わると思います。
また、「(あなたが)やってみせる。」場合は、
「みせる」の手話に方向性を示すことでよりはっきりします。
| ①(私が)やってみる。 | ②(私が)やってみせる。 | ③(あなたが)やってみせる。 |
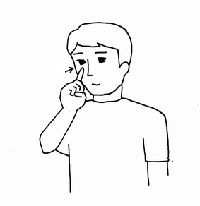 |
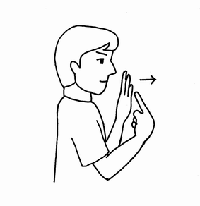 |
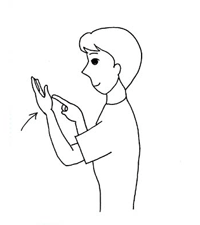
|
最後に、参考までに
「~してみる」には2つの手話表現があります。
| ~してみる | |
|---|---|
| A:①の文章で用いた表現 | B:「試みる」「工夫」などを意味する表現 |
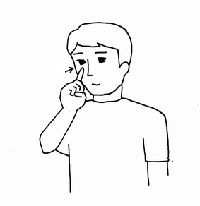 |
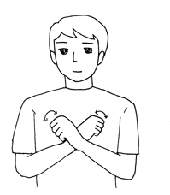 |
Bには「試みる(試験)」の意味が含まれ、
Aと比べると少し仰々しいイメージがあるといわれています。