| |
| 科学の教室② 講演会 |
| 「微生物と環境修復 ~微生物の秘められた可能性をもとめて~ 」 |
| 松村 吉信先生 (関西大学化学生命工学部 生命・生物工学科教授) |
| 2016年6月17日(金) 15:40~16:40 /本校224教室 |
|
| |
今年度第2回目の『科学の教室』として、関西大学化学生命工学部の松村吉信先生に講義をしていただきました。全校生徒に参加を呼びかけたところ2年生を中心に19人の生徒が集まりました。微生物という言葉を聞くと多くの人は病原菌や感染症を思い浮かべますが、一方で微生物は社会の様々な場所で役だっています。パンやアルコール飲料など発酵を利用した食品の生産、下水処理場における汚水の浄化、菌類からは抗生物質などの薬の生産など、微生物の様々な能力は人類の生活を支えています。そんな微生物の力を利用して環境汚染物質を分解するお話を中心に、微生物の研究についてお話をしていただきました。松村先生が大学で微生物を学ぶきっかけのお話から始まり、環境ホルモンが社会問題となる中でビスフェノールAを分解する微生物の研究、そして微生物による金属の腐食に関わって航空機や洗濯機にまで話題は広がりました。微生物の不思議な性質、遺伝子解析で分かる変異のしくみ、微生物の取り扱い方や研究方法など、微生物の力を活用することの可能性や難しさ、微生物を取り扱う研究の様子などがよく分かりました。
|
| |
 |
| |
 |
|
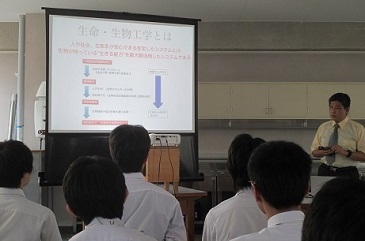 |
| |
|
|
 |
| |
 参加者の感想 参加者の感想 |
 大学では、日常的に生活しているありとあらゆるところで起こっている現象や、これから開発や発展していくような様々な研究が行われていることが分かった。また高校と違って自分で発見し、それについてきめ細かな所まで研究することが分かった。そういう意味では大学はすごく良い体験ができるし、良い学びの場だと思う。未来のためにも今しっかり勉強しないといけないと思った。(2年・女子) 大学では、日常的に生活しているありとあらゆるところで起こっている現象や、これから開発や発展していくような様々な研究が行われていることが分かった。また高校と違って自分で発見し、それについてきめ細かな所まで研究することが分かった。そういう意味では大学はすごく良い体験ができるし、良い学びの場だと思う。未来のためにも今しっかり勉強しないといけないと思った。(2年・女子)
|
 微生物は様々な事に利用できると分かった。微生物を利用した物質の分解や合成が将来発展していくように思えた。ビスフェノールAは中途半端な分解では、かえって毒性を増してしまうことも分かったし、微生物は活性酸素で死んでしまうが、まれに活動を休止してしまう微生物が耐性を持つことも分かった。遺伝子の配列が少しずれるだけで、その生物の性質が大きく変化することも分かった。(2年・男子) 微生物は様々な事に利用できると分かった。微生物を利用した物質の分解や合成が将来発展していくように思えた。ビスフェノールAは中途半端な分解では、かえって毒性を増してしまうことも分かったし、微生物は活性酸素で死んでしまうが、まれに活動を休止してしまう微生物が耐性を持つことも分かった。遺伝子の配列が少しずれるだけで、その生物の性質が大きく変化することも分かった。(2年・男子)
|
 ビスフェノールAの分解の問題点を見つけて、その問題点をゲノム解析によって解決しようとしたり、遺伝子組み換えをしたAOI株の機能がしっかりと働くように努力している姿勢が素晴らしいと思ったので、目標に向かって努力できるような人間になりたいと思います。(2年・男子) ビスフェノールAの分解の問題点を見つけて、その問題点をゲノム解析によって解決しようとしたり、遺伝子組み換えをしたAOI株の機能がしっかりと働くように努力している姿勢が素晴らしいと思ったので、目標に向かって努力できるような人間になりたいと思います。(2年・男子)
|
 今回の講演を聞くまで、金属では菌は繁殖しないと思っていました。しかし、菌は金属での繁殖はおろか金属の腐食に拍車をかけていることを知り大変驚きました。将来医療の現場で働くロボットを作りたいと思っているので、菌の付着しにくい素材を選ぶように心掛けることを覚えておきたいです。(2年・男子) 今回の講演を聞くまで、金属では菌は繁殖しないと思っていました。しかし、菌は金属での繁殖はおろか金属の腐食に拍車をかけていることを知り大変驚きました。将来医療の現場で働くロボットを作りたいと思っているので、菌の付着しにくい素材を選ぶように心掛けることを覚えておきたいです。(2年・男子)
|
 微生物が環境にある程度適応したり進化したりすることや、人間や人間が影響した環境との関係について最新の研究を知ることができた。とくに人間の生活が環境に及ぼす影響を、微生物の能力で解決するための研究などに興味をひかれた。(2年・男子) 微生物が環境にある程度適応したり進化したりすることや、人間や人間が影響した環境との関係について最新の研究を知ることができた。とくに人間の生活が環境に及ぼす影響を、微生物の能力で解決するための研究などに興味をひかれた。(2年・男子)
|
 微生物を使った環境の改善や、逆に微生物による被害を最小限にする研究の話を聞けたことで、微生物について具体的に知れたという事もありますが、一番聞いていて良いと思ったのは、「メリットの後の事を考える」という事です。そのことによって生まれる環境へのデメリットについて考えて、それを起こさないようにすることが大切だと思いました。(2年・女子) 微生物を使った環境の改善や、逆に微生物による被害を最小限にする研究の話を聞けたことで、微生物について具体的に知れたという事もありますが、一番聞いていて良いと思ったのは、「メリットの後の事を考える」という事です。そのことによって生まれる環境へのデメリットについて考えて、それを起こさないようにすることが大切だと思いました。(2年・女子)
|
 内容は少し難しい部分もありましたが、微生物の秘められた能力や上手な付き合い方などを知ることができました。大学ではそういった実験をたくさん行って、たくさんの発見や驚きがあると思うので、私もそういったところで学んだりできたらいいなと思いました。(1年・女子) 内容は少し難しい部分もありましたが、微生物の秘められた能力や上手な付き合い方などを知ることができました。大学ではそういった実験をたくさん行って、たくさんの発見や驚きがあると思うので、私もそういったところで学んだりできたらいいなと思いました。(1年・女子)
|
 微生物が人工物の環境ホルモンを分解したり、金属を溶かしてしまったり、身近にいる微生物が人々の役に立つように、未来に向けた研究をしておられてすごく関心が湧きました。松村先生のお話では「いま勉強できることはたくさんしておいてください。将来どれが役立つか分からないから」とおっしゃっていました。自分も松村先生のように目標を持って仕事ができるように、それを目指せるように何でも学んでいきたいです。(1年・男子) 微生物が人工物の環境ホルモンを分解したり、金属を溶かしてしまったり、身近にいる微生物が人々の役に立つように、未来に向けた研究をしておられてすごく関心が湧きました。松村先生のお話では「いま勉強できることはたくさんしておいてください。将来どれが役立つか分からないから」とおっしゃっていました。自分も松村先生のように目標を持って仕事ができるように、それを目指せるように何でも学んでいきたいです。(1年・男子)
|